最近、出版社の倒産が話題になりました。
得意先が破産すると、裁判所から「破産手続開始通知書」が届きます。
(届かないこともあります。その場合は、法人番号検索サイトで貸倒損失の確認ができる)
このときの対応をまとめました。
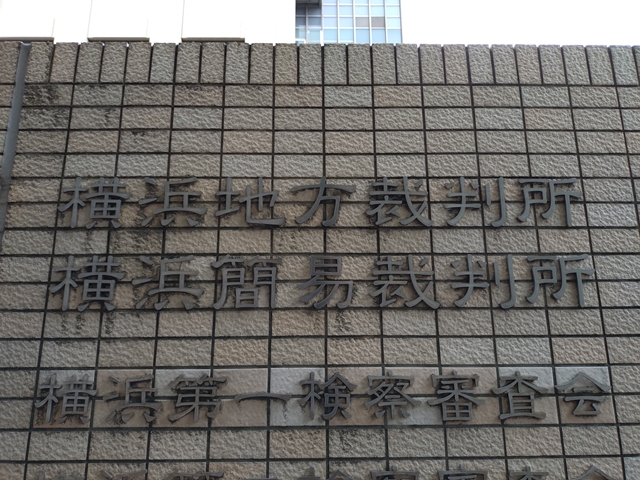
資金繰り:倒産防止共済の共済金借入
倒産する会社は、事前に兆候がある場合もあります。
入金が遅れがちになるとか、分割払いの申し出があるとか、悪いニュースが報じられるとか。
あとは、社長に会ったときに、どことなく様子がおかしいとか。
そういうことがあれば、何かしら準備ができるかもしれませんが、突然倒産してしまうこともあります。
すると、当てにしていた入金が急になくなるので、資金繰りの対策が必要になります。
破産手続開始通知書が届いていれば、本来の目的で、倒産防止共済を利用することができます。
共済金の借入れです(契約者貸付けではなく)。
数年前、倒産防止共済(縁起が悪いので、経営セーフティ共済という愛称あり)の加入が増えた時期がありました。
ひょっとしたら、いまも加入しているかもしれません。
当時から加入を続けていて、上限の800万円に達して掛留めになっている場合、掛金総額の10倍、8000万円(上限:実際の債権額)まで借り入れることができます。
とはいえ、実際の債権額が100万円なら、借りられるのは100万円です。
返済開始は半年後からで、その後54カ月にわたって返せばよく(借入額が5000万円以内の場合)、資金繰り上メリットがあります。
一時貸付金(契約者貸付け)では、掛金総額までしか借りられません。
掛金総額<債権額 の場合は、共済金借入のほうが有利です(掛金の権利は減少しますが)。
共済金借入は審査があるので、申し込みは早めがよいです。
一時貸付のほうが早く受け取れるなら、そちらを使う手もあります。
ただし、取引先の破産手続開始の申し立て日までに、半年以上の加入期間・共済金の支払いが必要です。
保険と違って、加入直後に倒産が発生した場合は、共済金借入はできません。
1年前納した場合でも、半年以上、加入期間が経過していることが必要です。
法務:破産債権届出書を返送
破産手続開始通知書に破産債権届出書が同封されていれば、すみやかに必要事項を記入して返送します。
破産した会社の財産から、債権額の割合に応じて配当が受けられる可能性があります(管財事件)。
届出書を返送しないと、配当が受けられませんので、忘れずに行いましょう。
この届出書が同封されていない場合もあります。それが、「同時廃止事件」の場合です。
この場合は、配当はありませんので、返送するものもありません。
税務会計:貸倒引当金、貸倒損失の計上
管財事件の場合、倒産した会社からは、弁護士を通じて配当がされます。
しかし、その額はかなり少額になってしまうことも多く、売掛金に、もはや額面どおりの価値はありません。
会社の純資産が減ってしまうということです。
税金は、原則として純資産が増えていれば増えます。減っていれば減るのです。
そこで、破産手続開始通知書が届いていれば、その売掛金は、税金の計算上、50%価値を減らしてよいことになっています。
100万円の売掛金が未入金のまま破産手続開始決定を迎えたら、最大50万円を経費にしてよいということです。
(担保や債務がある場合は、経費にできる額が減少します)
貸倒損失/貸倒引当金 の仕訳を入れ、その旨を税務申告すれば、50万円×税率分、納税が減り、資金繰りにプラスとなります。
自社の決算までに、最終配当があれば、引当金の仕訳は戻し入れて、配当分を回収後の売掛金残高を、 貸倒損失/売掛金とします。
さきほどの「同時廃止事件」の場合は、債権額の100%を 貸倒損失/売掛金 の仕訳とし、債権額がそのまま経費になります。
しかも、売掛金の貸倒れの場合は、消費税の納税も減ります。
仕訳の課税区分を、「課税売上貸倒10%」などと適切に設定しておきましょう(最終配当があった場合も同様です)。
近況報告
お客様にメール返信2件、Kindle本執筆、Netflix解約、その後税理士会に忘れ物を取りに行ったついでに、TINK ARCADE 横浜でリアルバウト餓狼伝説2の対戦会に参加。強豪の方に2回勝てて嬉しかった。
1日1新:同窓会会報に掲載する名刺広告の作成
1980年生まれ。木村将秀税理士事務所・代表。主にフリーランスやNPO法人のサポートをしている。自分で経理・申告したい/顧問税理士をつけたい/記帳代行を依頼したい に対応。特技はウォーキング(最長は戸塚~小田原間 45km 14時間)、趣味はジャズ喫茶巡り・村上春樹の本・SNK対戦型格闘ゲーム。プロフィール詳細
