NPO法人には、役員として理事・監事を置く必要があります。
法人から役員に報酬・謝金を支払う場合の源泉徴収事務についてまとめました。
法人税の申告をしていない場合(役員給与の損金不算入の影響がない場合)を想定しています。
なお、NPO法人は、役員の総数の1/3までしか役員報酬(管理費。役員としての地位にもとづくもの)を支払うことができません。
他方、理事が事務局職員を兼務していて、職員としての給与(事業費)を支給している場合は、この役員報酬に該当しません。
ただし、監事については、NPO法上、職員としての給与を支払えません。
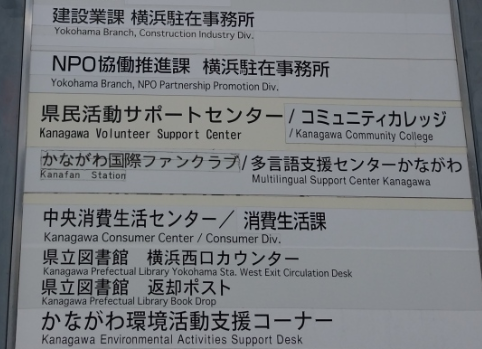
役員報酬を毎月支払う場合
設立当初から、毎月役員報酬を支払うこととしている場合には、設立時に「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を税務署に届け出ているかと思います。
すると、税務署から年末調整の時期に「給与所得・退職所得等の所得税源泉徴収高計算書(いわゆる源泉所得税の納付書)」が送られてきます。
有給の役員で、このNPO法人がメインの仕事先であれば、扶養控除等異動申告書を提出してもらい、月額表甲欄で源泉徴収し、年末調整し、源泉徴収票を発行する流れとなります。
原則、支払った月の翌月10日までに源泉所得税を納付します(納期の特例で半年に一度にできます)。
業務のつど日当を支払う場合
NPO法人の役員は、メインの仕事が別にあり、サブの仕事として理事・監事をされている方も多いです。
その場合は、扶養控除等異動申告書の提出がありません。
定款や役員報酬規程で、つど日当(定額のもの)を支払うとしている場合は、給与になります。
給与支払事務所等の届出をして、「日額表・乙欄」で源泉徴収・納付をします。
乙欄の人については、年末調整はしません。
無給の理事に講演の謝金を支払う場合
定款・規程で、役員報酬は無給としている場合です。
NPO法人として講演料を受け取り、役員に講演を外注し、役員に謝金を払うケースがあります。
この場合、内部の講師に対する謝金の規程を定めるなどしたうえで、謝金を支払い、講演料として10.21%の報酬の源泉徴収を行います。
講演料については、給与や士業報酬の源泉所得税の納付書と異なり、「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」を用います。
この納付書は税務署からは郵送されてきません。
納付書を税務署で入手するか、ダイレクト納付で納税を行いましょう。
また、報酬・料金の源泉所得税には、納期の特例(半年に一度の納付)の適用はありません。
必ず、支払った月の翌月10日に納付することになります。
無給の役員に支払う講演料(事業費)や、実費弁償の費用は、NPO法上の役員報酬(1/3規制)には該当しません。
なお、無給の役員が立替払いした費用を、NPO法人が実費弁償した場合は、源泉徴収は不要です。
総会シーズン 理事・監事への日当・交通費実費支給に源泉徴収は必要か – 税理士 木村将秀のブログ
編集後記
日本最大のヤマダ電機の店舗が近くにできたので、見に行きました。その後はZoom打ち合わせなど。
1日1新
・ゆうちょ通帳アプリ
・ゆうちょ認証アプリ
・ヤマダデンキ Tecc LIFE SELECT 横浜本店(戸塚区に移転オープンしたお店)
1980年生まれ。木村将秀税理士事務所・代表。主にフリーランスやNPO法人のサポートをしている。自分で経理・申告したい/顧問税理士をつけたい/記帳代行を依頼したい に対応。特技はウォーキング(最長は戸塚~小田原間 45km 14時間)、趣味はジャズ喫茶巡り・村上春樹の本・SNK対戦型格闘ゲーム。プロフィール詳細
