法人の決算書を拝見していると、「個別注記表が付いていないな」と気づくことがあります。
あと、「これ、あってもいいのにな」と思うものが付いてないことも。
それが、「個別注記表」と、「 『中小企業の会計に関する基本要領』の適用に関するチェックリスト」です。
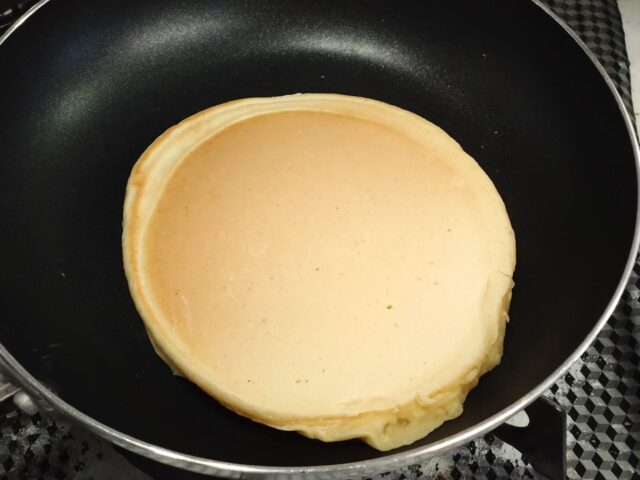
金融機関に見せるなら、義務は果たしておきたいもの
法人は、各年度で作成する義務がある書類があります。(会社法、会社計算規則)
- 貸借対照表(略称:BS)
- 損益計算書(略称:PL)
- 株主資本等変動計算書(略称:SS。合同会社は、社員資本等変動計算書)
- 個別注記表(略称:注記表)
ご自分の会社の決算書に、この4つが揃っているか、確認してみましょう。
意外とないのが、「個別注記表」です。
「個別」は「連結」と対比させるための言葉なので、ふつうの決算をしているだけなら、注記表でも意味はとおります。
上の3つは、会計ソフトが自動的に作成してくれます。
(株主資本等変動計算書は、会計ソフト上で残高の転記操作を要するものがあるので、操作もれに注意)
しかし、個別注記表だけは、何もしないと白紙か、出力されないことも多いのです。
もし、金融機関から借入をする予定だという場合は、個別注記表は作っておきたいところです。
会社法上、義務づけられている書類だからです。
これがないと、銀行などから「義務なのに作っていないのか……」と思われてしまうでしょう。
ちゃんとしているアピールは、大事です。
注記表の作り方
会計ソフトで、個別注記表の作成画面を開くと、真っ白な画面が出て、途方に暮れると思います。
多くの場合、テンプレートを表示することもできるので、それを直すことから始めたいものです。
ネットにも、テンプレートがあります。
「中小企業の会計に関する基本要領」ノンブル24ページ(PDF26ページ)
中小企業向けなので、このクラスの記載ができていればよいでしょう。
テンプレートが大企業向けだと、そぐわないことも多いので。
例えば、よくある「1株当たり純資産額」や「1株当たり当期純利益」が例示されていません。
社長がオーナーの中小企業では、あまり意味のない情報だからでしょう。
対銀行を意識したもので充分と思われます。
さらに私がアレンジすると、次のような感じでしょうか(すでに内容が若干古いのと、西暦に直すとすると)。
一例ですので、実際の会社の経理状況に合わせて、修正してお使いください。
個別注記表
自 2025年4月1日 至 2026年3月31日
1.この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。
2.重要な会計方針に係る事項に関する注意
(1)資産の評価基準及び評価方法
①棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法を採用しています。
(2)固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物、2016年以降に取得した建物附属設備
及び構築物は定額法)を採用しています。
②無形固定資産
定額法を採用しています。
(3)引当金の計上基準
①貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について
法人税法の規定に基づく法定繰入率により計上しています。
②賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分
を計上しています。
(4)その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
①繰延資産の処理方法
開業費 支出時に全額費用として処理しています。
②消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっています。
3.貸借対照表に関する注記
(1)有形固定資産の減価償却累計額 ○○円
(2)担保に供している資産および対応する債務
土地 〇〇円
長期借入金 〇〇円
4.株主資本等変動計算書に関する注記
(1)当事業年度の末日における発行済株式の数 〇〇〇株
通常、税務署に何も評価方法の届出をしていなければ、棚卸資産は最終仕入原価法、固定資産は定率法(法人。一部定額法)になっているはずです。
繰延資産の処理方法は、実際にその処理があった年度だけ書けばよいでしょう。
貸借対照表に関する注記でいうと、実務上は、減価償却累計額を貸借対照表に載せるほうが珍しいので、個別注記表に記載することになります。
毎年の決算の内容ごとに、注記の記載は変わります。
毎回、前年のコピペにならないようにしたいものです。
担保に入れている土地があれば記載することも、銀行や信用金庫などへの情報提供として必要です。
減価償却費や引当金の計上、繰延資産の費用処理が行われると、費用が増え、利益は減ります。
それでも毎期、これらの費用を計上する姿勢を見せれば、強い会社アピールになります。
赤字がちの会社は、これらの費用処理を積極的に行わないことが多いからです。
PLは、プロフィット・アンド・ロス・ステートメント。その会社の声明です。
何をアピールするかは、自分で決められるのです。
税理士に「中小会計要領チェックリスト」もつけてもらおう
個別注記表の冒頭に、「中小企業の会計に関する基本要領」として、決算書が則っている会計基準を明示します。
決算書を読む人(銀行など)は、この基準をもとに、数値を見るからです。
中小企業であれば、この会計基準(いわゆる「中小会計要領」 )を使うことが一般的です。
税理士がついている会社であれば、さらに「 『中小企業の会計に関する基本要領』の適用に関するチェックリスト」も付けている場合があります。
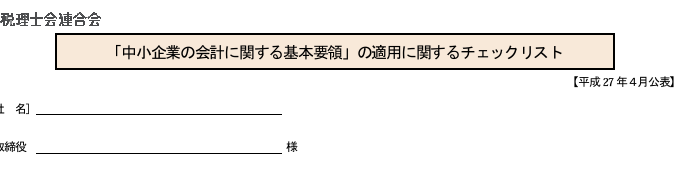
これも、意外とつけている会社は少ないです。
以前は、チェックリスト融資といって、信用保証協会の保証料の割引が受けられたのですが、いまはほぼないので……。
ただ、金融機関から求められるケースもまだあります。
チェックリストの「YES」が多ければ、会社の利益と財産の額が、一定の信頼性をもって計算されていることのアピールになります。
チェックリストに「NO」がついたら、税理士が所見欄に理由を書いているはずです。
NOを減らしていけるよう、改善策を税理士と話し合ってみましょう。
融資を受けようという中小企業の決算書は、基本、うたがわれています。
そのため、信頼を得るための試みは、ひとつでも多くやって損はありません。
近況報告
お客様にメール2件、電話1件。
仕事の依頼フォームの動作チェックなど。
1日1新:お客様に提供しているインポート用Excelシートの修正
1980年生まれ。木村将秀税理士事務所・代表。主にフリーランスやNPO法人のサポートをしている。自分で経理・申告したい/顧問税理士をつけたい/記帳代行を依頼したい に対応。特技はウォーキング(最長は戸塚~小田原間 45km 14時間)、趣味はジャズ喫茶巡り・村上春樹の本・SNK対戦型格闘ゲーム。プロフィール詳細
