簿記はある程度勉強したとか、習うより慣れよでなんとなく会計ソフトに入力できている、という方にこそ、確認していただきたい簿記のルールがあります。
車の運転も、事故を起こすのは慣れてきたときといいますから。
いま、あまり参照されることもありませんが、その名も「企業会計原則」といいます。
いくつかありますが、大事なものだけ。
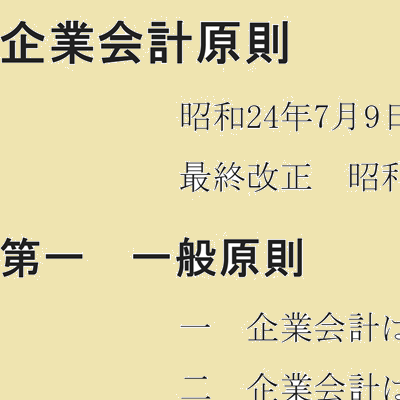
真実性の原則
「企業会計原則、どれがいちばん好き?」と聞かれたら、「真実性の原則」と答えたいところです。
企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない。
企業会計原則(大蔵省企業会計審議会、1982年)
1982年から何ら変わっていませんが(別の企業会計基準に上書きされていますが)、いまでも会計学の教科書には必ず載っているものです。
企業会計、会計、会計学というのは、簿記を含む大きなカテゴリーの名前と考えていただければいいです。
真実というとかっこよすぎますし、真実なんて唯一のものがあるか? という疑問も出てくるかと思います。
ここでは、簿記や会計には、ルールがあり、ルールを守ることで、より真実に近づいていく、という程度の意味です。
また、当然のことですが、ウソを入力してはいけないという意味もあります。粉飾決算(利益を実際より増やす)、逆粉飾(利益を実際より減らす)はNGです。
簿記の基本的なルールを守らないと、入力もできない
会計ソフトを使うと、基本的に、間違った入力はできません。
貸借平均の原理(簿記の世界では、なぜか、左右が一致することを平均といいます。アベレージの意味ではなく)というルールもあります。
単純に、仕訳は、借方の金額と貸方の金額が一致していないと、データとして受け付けませんよ、ということです。
基本的なことですが、手書きではスルーされる誤りが、ソフトを使うとぜったいにないので、そこは安心であるとも言えます。
あとは、資産の増+負債の減という仕訳も入れられません。どちらも借方に入れるもので貸方が0円となり、貸借が一致しないからです。
反対に言うと、借方に資産を入力したら、貸方は、資産の減少・負債の増加・資本(純資産)の増加・収益の増加・費用の減少であれば入れられるわけです。
これで貸借の金額が一致していれば、間違っていても会計ソフトのチェックはスルーしてしまうわけです。
振替伝票の入力モードでは、この辺の基本がわかっている必要があります。
会計ソフトに、ウソを入力してはいけない
当たり前すぎて、言われませんが、ウソを入力するのはダメ、というのが真実性の原則です。
ウソというのは、実際の取引と違うものを入力するということです。
よくある粉飾決算のパターンとしては、「借入をして預金残高が増えたら、相手科目は借入金になりますが、ウソをついて売上高にする」というものです。これで会計ソフトの入力は通りますが、ぜったいにやってはいけません。
それで決算書の見た目は良くなるかもしれませんが、それを使って銀行からお金を借りたら、詐取したことになります。
ふつうに犯罪ですので、逮捕されて、起訴されて、新聞沙汰になります。
と考えると、会計ソフトの入力一つとってみても、深いですね。入力しだいで犯罪ですから。
脱税も、最終的は犯罪になって、それが消費税がらみだと、インボイス登録ができなくなり、B2B取引から排除されるというペナルティもあったりします。
インボイス登録「消費税法に違反して罰金以上の刑に処せられたことはありません」とは – 税理士 木村将秀のブログ
当たり前のことも、あたらめて意識しつつ、会計ソフトに向き合ってみましょう。
編集後記
今日は、ホームページから単発相談のご依頼をいただいたので、受け方のご提案をしました。
1日1新:餓狼伝説 City of the Wolves 。26年ぶりの新作、その演出に思わず涙が……。
1980年生まれ。木村将秀税理士事務所・代表。主にフリーランスやNPO法人のサポートをしている。自分で経理・申告したい/顧問税理士をつけたい/記帳代行を依頼したい に対応。特技はウォーキング(最長は戸塚~小田原間 45km 14時間)、趣味はジャズ喫茶巡り・村上春樹の本・SNK対戦型格闘ゲーム。プロフィール詳細
