昔のエピソードで、だいたいの人に驚かれるのは、「高校受験のとき、滑り止めを受験しなかった」」ことです。
公立高校1校だけ受験しました。
試験の当日に風邪を引いたらどうするつもりだったのでしょう……。
当時は、中学校生活・成績の内容で合否がほとんど決まったので、できた技ではありますが。
ある意味、中学生活自体が保険だったのです。
昔から「保険をかける」ことに関心が薄い性格だったのかもしれません。
いまも、私はほとんど保険に加入していません。
事業を経営していると、保険を勧められがちですが、あえて「勧めない」という視点で書いてみました。
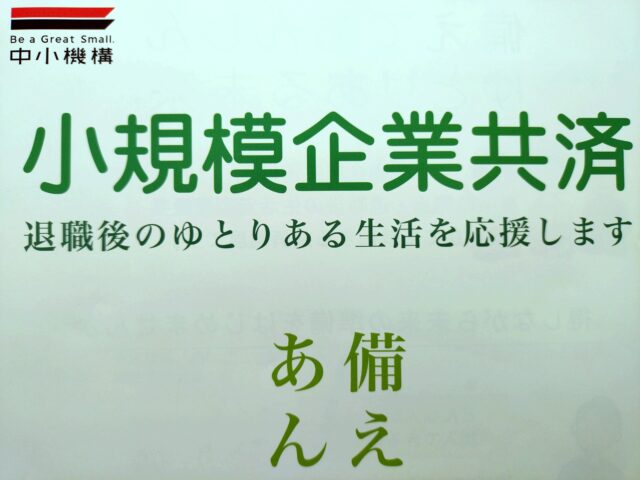
税理士事務所から保険を勧められたら
顧問税理士の担当者から、決算のときに事業用の保険を勧められたことはありませんか?
もちろん、必要があれば加入したらよいですし、断っても顧問サービスに支障が出ることはないので、社長が判断していただければと思います。
断って、一時的に気まずい気持ちになるかもしれませんが、ここはご自分の意思をしっかり持ち、必要性以外で、判断に影響させないようにしましょう。
一般に、自分の内実をよく知っている相手から金融商品を勧められる状況は避けたいものです。
税理士事務所の勧める保険以外も調べておきましょう。
私は個人の税理士事務所をやっていますが、保険代理店にはなっていないので、お客様に保険を勧め、それにより手数料を得ることはありません。
保険に入らないという選択肢を持つ
「保険に入らない」という選択肢を常に残しておくことをおすすめしています。
もちろん、保険には、保険でしか得られないメリットがあります。
自動車保険(任意)のように、万一のときに高額な賠償が予想されるもので、絶対に入るべき保険もあります。
加入すれば、その後は保険事故発生で、即、保険金が規定どおりに支払われる機能は、他に代えられません。
リスクを、保険料として払った金額に確定する効果があると言われます。
ただ、事業用の保険は保険料も高いので、それを払わなければもっとお金が貯まるはずです。
そして、貯まったお金そのものが、事業の保険となります。
ということであれば、金融機関から借入れをすることも保険の一つ、利息も保険料と考えることも可能です。
利息は保険料同様、経費になります。
利息が保険料より安いなら、借入れも有効です。特に、業績が伸びているときは。
業績が好転してきたら、借入れを検討しよう – 税理士 木村将秀のブログ
保険金の割に、あまりに保険料が高いと感じるものは避けましょう。
だったら、預金でカバーできないか、考えるのです。
この預金残高のように、保険商品以外で、保険的な機能を果たすものはいろいろあります。
また、自分自身の個人の死亡保険はどう考えるか。
ポイントは、自分が死亡したときに、本当に、保険金以外に残された家族を助けてくれる人・モノは存在しないのか、という視点を持つことです。
他でカバーできないものについて、保険に入るようにすれば、定期的な支出を抑えられるでしょう。
小規模企業共済も保険になる
個人の生命保険に関して言うと、生命保険料控除というものがあり、払った保険料のうち上限12,000円までは所得を減らす効果があります。
国の保険制度だけではなく、民間の保険を普及させることで、社会の安定化を促進するという趣旨の制度です。
しかし、事業者の方であれば、もっと優先して加入すべき保険があり、それが小規模企業共済です。
スモールビジネスの経営者の退職金を積み立てるための共済ですが、実質的には死亡保険と同じ効果があります。
個人事業主だけでなく、法人の経営者も加入できます。法人成りにも対応しています。
生命保険料控除のように、小規模企業共済等掛金控除というものがあり、こちらは上限がありません。
払った金額がそのまま個人の所得(社長なら役員報酬。法人の利益には影響なし)から控除されます。
小規模企業共済であれば、最大月額7万円、年840,000円が控除されます。
節税の観点では、生命保険との大きな差があります。
しかも、1年以上掛金を払えば、それを借入のかたちで現金化もできるので、状況の変化に強いです。
最大の注意点は、会社の規模が大きくなると、加入できなくなってしまうことです。
事業を始めて、利益が見込まれる状況になったら、早めの加入を検討しましょう。私も加入しています。
しかも、マイナンバーカードとカードリーダーがあれば、誰にも会わずに小規模企業共済に加入したり、掛金を変更したりでき、非常に気楽です。
小規模企業共済の申込みは、オンライン手続きで! – 税理士 木村将秀のブログ
まずは無理のない金額(月額1,000円から)で加入し、事業の伸びに応じて掛金を増やしていくのがよいでしょう。
ただ、利益が決算まで予想できないと、先んじて加入することができません。
急に税金が増えると、必要以上に不安になるものです。
そこで、月次決算、(四)半期決算をして、利益を見えるようにすれば、小規模企業共済により、機動的な節税が可能となります。
月次決算をすれば、自分の数字やお金をコントロールしている感覚を得ることができるのです。
近況報告
日曜なので、『ふつうの軽音部』の最新話をチェック。その後ブログセミナーを受講。
「餓狼伝説 City of the Wolves ランクマッチ」は B-II から B-III をうろうろ。
昼食時にウェイン・ショーター「Celebration Vol.1」を聴く。Vol.2の予定はまだか……。
昨夜届いたお客様のメールに返信。
1日1新:WordPressプラグイン Table of Contents Plus
1980年生まれ。木村将秀税理士事務所・代表。主にフリーランスやNPO法人のサポートをしている。自分で経理・申告したい/顧問税理士をつけたい/記帳代行を依頼したい に対応。特技はウォーキング(最長は戸塚~小田原間 45km 14時間)、趣味はジャズ喫茶巡り・村上春樹の本・SNK対戦型格闘ゲーム。プロフィール詳細
